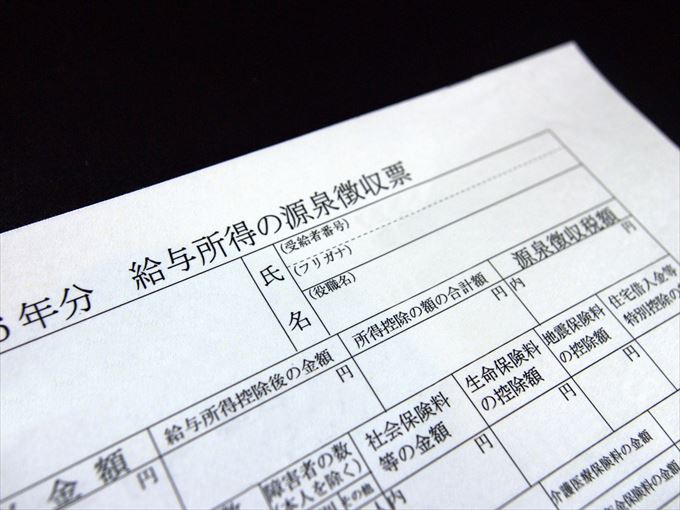
給与明細の保管はどれくらいの期間しておく義務があるのでしょうか?
これは、従業員を雇用する側(事業主)が雇用している従業員の給与明細を保管する義務の有無についてです。
どの会社であれ人材を雇っている場合、必ず毎月、雇用している従業員に渡すのが給与明細であり、雇われている側(従業員)にいれば毎月、雇用する側(事業主)から頂くのが給与明細です。
雇用する側が給与明細の保管義務について、充分に理解しているかどうかは、いざという時に雇用する側(事業主)、雇用される側(従業員)の両方にとって大きな問題に発展する可能性があります。
なぜなら、雇用する側(事業主)として、後で給与明細に関わる内容で何か証明を出さなくてはいけないこともありますし、その辺の対応において曖昧な知識しかないと、雇用される側(従業員)の給与明細の保管義務において職場で規定をきちんと示されてない場合には、どんな風に保管しておけば良いのか担当者が困っていては問題です。
雇用する側(事業主)が給与明細の保管をどれぐらいの期間しておく義務があるのかを、雇用される側(従業員)も同時に知っておくことが必要です。
雇用される側(従業員)に立っての給与明細の保管期間や保管方法についても後程、例をとって説明します。
では、法律の観点から見て、雇用する側(事業主)に、給与明細の保管期間に義務があるのかないのか、あるのならば、どれくらいの保管期間なのかを見て行きます。
また、雇用する側(事業主)が給与明細の適切な保管方法はどうあるべきなのかも見て行きます。
目次
給与明細の書類の保管義務は?
<法律上の義務> 給与明細の中身をひも解く
賃金台帳の保管期間は3年間、税法上では保管期間は7年間
職場内でも稀に聞くこともあれば、ネット上を検索すると、賃金台帳の他に給与台帳という言葉が出てきたり、保管義務が3年間と7年間とどちらもあったりして理解しにくいと感じます。
給与明細は一般的によく聞くワードですが、給与台帳や賃金台帳となると、なかなか特定の時以外は聞くことが無いはずです。
名前の違いは、記載された内容が労働基準法に基づいた項目がある場合に、賃金台帳になります、給与掲載分しか記載されてない場合ですと給与台帳になります。
賃金台帳の保管期間は、[労働基準法に定められた年数]と、[税制法に定められた年数]の違いによるものです。
簡単に解釈すると、一般の給与明細の内容に加えてより細かい情報を盛り込んだ書類であるのが賃金台帳であり、給与明細よりも簡素な情報のみであるのが給与台帳であります。
つまり、それらは記載内容により、給与台帳や賃金台帳と呼ばれると覚えておくと良いです。
「労働基準法では3年間の保管義務」(労働基準法109条)
賃金台帳を3年間保管する義務があり、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間、残業・休日出勤の状況、基本給・手当て、控除について記入されている必要があります。
個人別の給与明細書を保管する必要はないですが、一覧としての賃金台帳としての保管はしておく必要があります。
注意: 保管義務を怠ると罰則があります。
罰則は、30万円以下の罰金です。
法律上で3年間の保管する義務があるわけですが、あくまで最低限の期間を示します。
「国税通則法では7年間の保管義務」
国税通則法で7年間の保管義務がある書類としては、源泉徴収簿、扶養・保険・配偶者特別控除に関わる書類となっています。
先程、3年間と7年間の保管期間の違いがあるのは、賃金台帳に記載された中身に、上記のような内容が含まれているかどうかで決まります。
この場合は、賃金台帳に源泉徴収簿、扶養・保険・配偶者特別控除が内容に含まれていますから、国税通則法により7年間の保管義務が生じます。
そこで、何か問題が起こると面倒なので、労働基準法に基づく3年間の保管期間で賃金台帳を処分せずに、国税通則法に沿って7年間、賃金台帳を保管しておくのが無難です。
以上、給与明細の書類の保管義務について法律の面から説明しましたが、少しは理解ができましたでしょうか?
雇用する側(事業主)、雇用される側(従業員)の両方にとっても重要な内容です。
労働基準法における賃金台帳を作成する義務について
賃金台帳における法律: 第108条と第54条を読んで下さい。
労働基準法 第108条
使用者は、事業場ごとに「賃金台帳」を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額
その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
労働基準法 施行規則 第54条
使用者は、法第108条の規定によって、次に掲げる事項を労働者各人別に「賃金台帳」に記入しなければならない。
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
7.基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8.法第24条第1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
どんな風に給料明細の書類を保管しておくのがベスト?
賃金台帳は、労働基準法から言うと3年間の保管義務となっていますが、税制に関わる書類の保管義務は7年だと言うことがわかります。
給与明細の台帳は、源泉徴収票や税の控除に関わる部分は7年間保管しておく必要がありますが、会社によって必要項目を分けて賃金台帳と給与台帳としている場合もあります。
この場合は、労働基準法に関わる項目を集めてある給与明細の台帳は3年間保管、源泉徴収と納税処理に関する給与明細の書類は7年間保管としておけば良いです。
きっちりと、労働基準法と国税通則法の項目を分けた給与明細の台帳を2つ保管しているのであれば、労働基準法に基づいた給与明細の台帳は3年間のみの保管で済みますが、先ほども話したとおり、はっきりとしない場合は、給与明細の台帳は7年間保管しておくのが良いです。
個人において給与明細を保管しておく意味
これまでに受け取った給与明細を保管していますか?
事業主から頂く給与明細を誰しも確認はしますが、人によっては確認するだけで、きちんと保管をしてなかったりする人もいます。
給与明細には、いざという時に役立つ情報が記載されていますから、保管しておくことをオススメします。
給与明細に記載されている大切な内容を確認と、保管理由
給与明細に記載されている内容で、特に大切なのが、年金保険料・所得税・住民税の確認です。
年金保険料について
厚生年金に加入していれば、毎月、厚生年金保険料が給与から引かれています。
事業主が厚生年金保険料を充分に年金事務所へ支払っていなかったりすると、貰えるはずの年金額が貰えないなんてことが後になり起こります。
しっかりと、どれだけの厚生年金保険料が給与から引かれているのかを確認することと共に、給与明細を保管しておけば、年金受給において問題が生じた時の証明となります。
また、最近、問題になっている厚生年金の未加入問題の発覚にも役に立ちます。
給与明細を保管してないことから、逆に国民保険料を追納しなくてはいけないなんてことも実際に起こっています。
これは、事業主が厚生年金をきちんと支払っていなかったことが原因ですが、証明となる給与明細を保管していなければ、自分の身を守ることが出来ないです。
所得税・住民税について
給与明細を見れば、その月の所得税・住民税が給与からどれだけ引かれているのかを確認できます。
その月にいくら所得税・住民税が引かれているのかも前月と比較して正しいのかどうかを確認するためにも給与明細の保管が望ましいです。
最近は、紙面でなくWEB上での給与明細を知らせる形に移行している企業も多いです。
給与明細のデータはいつでも社内専用のパソコンから確認はできますが、月々の給与明細をプリントアウトして個人でも保管しておくのが良いです。
コンピューターが作業をしてくれる時代です。
給与明細の計算や詳細についての記載もコンピューターが自動更新してくれますが、最初のデータ入力は人間がしますから、必ずミスはあります。
ミスがあるかもしれないという概念で給与明細を確認し、保管する習慣をつけることです。
また、事業主である会社が突如、倒産するケースがあります。
そうなると、すぐに失業保険の申請が出来ない・未払いの給与を請求できないなどの問題が生じます。
そうした時に、給与明細を保管しておけば、これまでの証拠になりますから手続きがスムーズに行えます。
個人の給与明細において、確定申告を考えると、さかのぼって申請できるのが5年ですから、それ以上、保管しておいても意味がないと考える人もいます。
給与明細の保管を5年間で区切るのか、念の為に5年以上保管するかは個人の考え方しだいです。
年金問題で大騒ぎになり被害を被った人がたくさんいる日本の社会保障ですから、保管可能であれば、給与明細を長年保管しておくのが安全と言えます。
個人における給与明細の保管方法について
紙面の給与明細、WEB上からプリントアウトした給与明細
とにかく、いつ必要になるかわからない大切な給与明細ですから、すぐに参照できるような保管方法をとります。
まずは、給与明細をクリアファイルに溜めて行きます。
一年経てば、その一年分をクリアブックに保管し、色分けもして、外から見て年度がすぐに確認できるようにしておきます。
保管場所がないという方、電子データとして保管する方法もあります。
最近ではデータ化してパソコン上に保管する保管方法をとる方も多いです。
給料明細をスキャンしてPDF化してデータとして保管しておくのです。
また、給料明細と別に源泉徴収表も必ず保管しておきます。
源泉徴収票は意識して保管している人が多いかもしれませんが、保管方法が適当だと、必要な時にどこに保管したかで右往左往していると大変ですから、これを機会に保管方法を見直すのも良いです。
給与明細の見方・手取り金額の計算方法を理解しておくこと
事業主と契約する時に、契約上を元に説明を受けますが、説明は一部に過ぎないです。
給与明細がどのように決められているのかを理解しておくことです。
契約前に提示されていた基本給の金額が残業代を含んでいたりします。
残業代・出張代における計算方法や休日出勤における給与への反映がどうなっているのかを知る為には給与明細の見方を把握しておくことです。
契約時にそこまで細かく給与について説明を受けることは、まずないですから、契約書を元にして給与明細を確認し手取り金額が予想していた金額と正しいのかどうか自分でも計算してみることです。
契約社員、派遣社員、パート社員、正社員に関わらず、手当における計算ミスをされて頂ける手取り金額を受け取ってないケースは多々あります。
そんな時に、なんとなく少ないと感じるというのでは損をしますから、その点でも毎月の給与明細を手にしたら、自ら見て確認作業をします。
出張により先に出費した金額が後払いになっている支払いについては特に注意します。
まとめ
○労働基準法に関わる給与明細の書類は3年間の保管義務がある
○国税通則法では7年間の保管義務がある
◯個人においても給与明細を保管することと、その保管方法を考える
◯個人の給与明細の見方・手取り金額における計算方法を知る
労働基準法で決まった項目を記載した賃金台帳は3年間の保管義務が定められています。
一方、国税通則法では納税に関係する源泉徴収や控除に関する書類に7年間の保管義務が定められています。
個人においても給与明細は、保管しておくべきです。
毎月の年金保険料・所得税・住民税を確認するクセもつけます。
毎月分を個人でも保管し、クリアファイル・クリアブックで保管する、電子データ化(PDF)として保管する。
年ごとにまとめて最低5年間は保管期間を設けて、いつでも参照できるようにする。
給与明細は、一度発行されると、それが正となります。
個人がその事業所(会社)で働いた証明書ですから、最低限の給与明細の見方を把握しておくべきです。