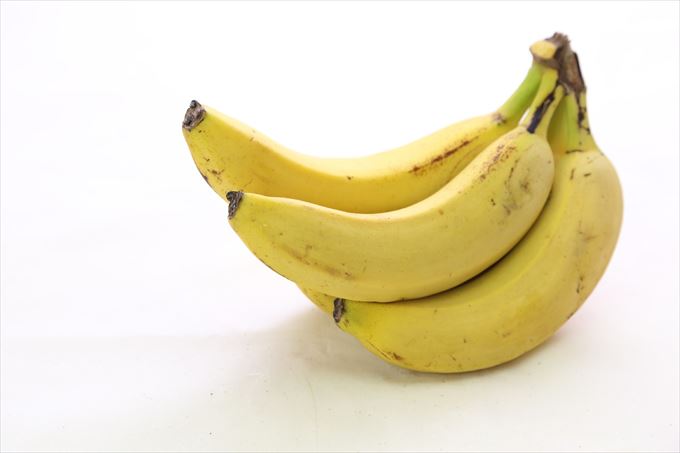
バナナはダイエットにも、健康作りにも欠かせない食材ですね。
一房でまとめ買いしても結局傷んでしまうから、少量ずつ買っているという方も多いのではないでしょうか?
バナナの新しい保存方法について、驚きの保存方法が話題になっているんですよ!
「つり下げた方が長持ちなんてもう古い!」
最新のバナナの保存方法についてまとめていきます。
目次
バナナの保存方法のいろいろ
つり下げて保存する
おなじみバナナハンガーなどで房の頭を引っかけて吊して保存します。
バナナ自身の重みで実が傷んでしまうのを防いで長持ちにつながります。
1本ずつラップに包む
房のところを切り離すと2~3日ほど長持ちします。
1本ずつラップで包むことでエチレンガスの影響を受けにくくなり、成熟を緩やかにする事が出来ます。
房の頭だけをラップで包む
房がつながっていても、くっついている部分だけをきっちりラップで巻くだけで、成熟を緩やかにする事が出来ます。
房の上の頭の部分がつながっていると、エチレンガスの発生しやすくなります。
1本ずつ切り離し上のところを切り落とす
房につながっていたところがない方が、成熟を遅らせることが出来ます。
そして最も驚きの保存方法がこれです。
バナナを50℃のお湯につける
バナナが浸かる、50℃のお湯を用意します。
そこに、5分ほどバナナを浸けて取り出し、1時間室温で放置します。
ポリ袋に入れて、冷蔵庫の野菜室で保管すると2週間は持ちます。
何もせずに冷蔵庫で保存すると皮が黒くなってしまいますが、50℃のお湯に浸けたバナナは黒くなりにくくなります。
また、熱を加えることでバナナの甘みを増すことが出来るので、おいしさもアップします。
保存期間が長くなる上、おいしくなるなんてやらないと損する画期的な方法ですね。
沸騰したお湯を同量程度の水道水で割ると50℃~55℃になりますから、温度計がない場合、冬なら同量程度、夏なら同量よりやや多めと考えると良いでしょう。
バナナの保存方法のポイントとは
バナナの熟成は、バナナ自身が出すエチレンガスによって進められます。
バナナを長持ちさせる保存方法で一番のポイントとなるのは、
『エチレンガスにさらさないこと』です。
バナナのエチレンガスが出やすくなる条件とは…
・室温が高いとき
・硬いところに置くなど、バナナに圧力がかかっている時
・バナナが房ごとくっついている状態の時
ラップで房の頭をくるむと、エチレンガスの発生を抑えることが出来るので、熟成が緩やかになります。
輸入されたバナナを出荷のタイミングに合わせて熟成させるプロの業者も、温度、湿度、換気(酸素の供給)を整えてエチレンガスの発生を管理し、バナナを熟成させて出荷しています。
日本で流通しているバナナは、エクアドルやフィリピン等の海外からの輸入品です。
植物免疫法という法律のため、熟したバナナを輸入することが出来ないため、バナナは青い状態で輸入され、国内のバナナを扱う業者が、バナナ加工工場で、エチレンガスをコントロールして食べ頃の状態で店頭に並ぶようにしています。
ですから、家庭でのバナナの保存方法としては…
・長持ちさせたいとき⇒エチレンガスに当てない、発生させない
・早く熟成させたいとき⇒エチレンガスにさらす
と覚えておくと良いですね。
リンゴはエチレンガスを多く出すので、早く熟成させたいときには、リンゴと同じポリ袋に入れておくと良いのです。
バナナを房ごと一緒においておくと、隣合ったバナナの実がお互いにエチレンガスを出しているので、熟成が進みやすいというのも、わかる気がしますね。
エチレンガスとはどういうものか
エチレンというホルモンの影響で、果物や野菜はエチレンガスを発生しています。
エチレンは、植物の生長に欠かせない物質ですが、収穫後は、老化を進め果物や野菜そのものを腐らせていきます。
多くのエチレンガスを発生させることで有名なのがリンゴです。
このため、リンゴと一緒に保存した果物や野菜は、エチレンガスの影響を受けることになり、日持ちが悪くなる傾向があります。
エチレンガスが発生すると、果物は熟成が進む分、腐敗のタイミングも早くなりますし、ブロッコリーやきゅうりが黄色くなりやすくなります。
冷蔵庫で野菜を保存するときに、長持ちさせたい場合には、リンゴと一緒にしない方が良いのです。
キウイやマンゴーなどを早く熟成させたいときには、バナナ同様、同じポリ袋に入れてみましょう。
野菜や果物を50℃のお湯に浸けると…
バナナを50℃のお湯に浸けるなんて、ちょっと衝撃的な保存方法ですよね。
50℃のお湯にバナナを浸すことで、ヒートショックプロテインが作られ、バナナ自身の免疫力が高まります。
このため、エチレンガスが出てもバナナは影響を跳ね返し、食べ頃な状態を保つ事が出来るのです。
50℃のお湯で野菜を洗うと、しなびかけていても活力を与えて日持ちを良くするといった効果があります。
50℃という温度は、野菜や果物を元気にする効果がある絶妙な温度なのです。
・50℃洗いで、野菜がパリッとする
・汚れが良く落ちて、味が良くなる
・洗った後、日持ちが良くなる
・イチゴなどの甘みが増す
なんと、バナナ以外の野菜や果物でも試したくなるような、すごい効果があります。
温度と食品の関係を長年研究してきた研修者も、50℃洗いや50℃蒸しで、野菜がしゃきっとするということをTVなどで紹介していますね。
『長野県で野沢菜を温泉で洗うとしゃきっとする』
『別府温泉の湯気に野菜を当てるとしゃきっとする』
昔の人は、50℃のお湯で野菜をおいしくする知恵に気付いていたといいますから、その知恵はすごいものです。
50℃というのは、細胞を破壊せず組織をしっかりさせたり、葉物野菜の気孔を開いて水分を復活させることが出来るので、シャキッとするのです。
これは科学的にも検証されていることです。
不思議な感じがしますが、50℃のお湯の効果は、驚きのパワーを持っていると感じさせられます。

バナナの味・栄養価を高める保存方法とは
バナナの日持ちを良くするための保存方法のポイントは、
『エチレンガスを抑えること』
『50℃のお湯に浸す』
と言えそうです。
保存性を良くするだけでなく、味・栄養価を引き出すための保存方法をまとめて見ましょう。
50℃のお湯に浸ける
50℃のお湯に5分浸けて、1時間室温で放置します。
保存性が良くなるだけではなく、味にも変化があるのですね。
酵素の働きでバナナの中のでんぷんが変化して、甘みが増します。
エチレンガスを抑えて保存性を増すだけでなく、糖度が上がって味にまで変化が出てきます。
ちなみにバナナはおしりからむいた方が甘みが増します。
これは、花の先にあたる部分なので、栄養が集まりやすいからだと言われています。
サルも先端からむくのだとか…
冷凍すると栄養価が高まる?
バナナはマグネシウムやポリフェノールなどが豊富ですが、冷凍することでこれらの働きが高まると言われています。
ポリフェノールは、抗酸化作用に優れている物質です。
抗酸化作用が優れた食品は、活性酸素を取り除くのに役立つので、生活習慣病やがんの発生リスクを下げるに役立ちます。
皮をむいてラップでくるんで冷凍しても良いですし、スライスしたバナナをラップに挟んで数枚ずつ取り出せるようにして冷凍してみましょう。
1ヶ月ほど保存することが出来ますし、次のように利用する事が出来ます。
・半解凍でそのまま食べる
・冷凍のまま牛乳とジューサーにかけてスムージー
・半解凍でパンケーキやマフィン生地に混ぜる
バナナの食べ方と保存方法
バナナを買ってきたら、食べ方と保存期間を考えて保存方法を選ぶと良いですね。
そのまま1週間以内に食べるとき
房を切り離すか、房の頭をラップでくるむ
そのまま1週間を越えて食べたいとき
50℃のお湯に浸けてラップに包んで冷蔵庫の野菜室に入れる。
2週間以上保存でアレンジして食べる
皮をむいてラップにぴったり包んで冷凍する。
マフィンやケーキにして冷凍にするという方法もオススメです。
*バナナケーキレシピ*
<材料>
A
バナナ2本
レモン汁 少々
B
砂糖 1カップ
卵 2個
牛乳大さじ2
サラダ油 大さじ4
小麦粉 1.5カップ
ベーキングパウダー 小さじ1
塩 小さじ1/4
バニラエッセンス
<作り方>
① バナナをボールに入れて、レモン汁を振って泡立て器でつぶす。
② B以下の材料を順に混ぜ合わせてぽってりとしたクリーム状になるようにまぜあわせる。
③ マフィン型に入れて180℃のオーブンで20分ほど焼きます。
混ぜるだけの簡単レシピなので、サッと作ってあら熱が取れたら、ラップで包んでジッパー付きの袋に入れて冷凍しておけば、小腹が空いたときや、子どものおやつにすぐに食べることが出来ます。
まとめ
バナナのオススメの保存方法は、エチレンガスにさらさないこととヒートショックを与えることがポイントです。
○ バナナの房の頭をラップできっちり包む
○ 50℃のお湯に5分浸けて、1時間室温で放置したものをラップに包んで冷蔵保存すると2週間ほどもつ
○ 冷凍したものは、半解凍、スムージー、お菓子に活用出来る
バナナラックに吊したり、皮が黒くなるのを覚悟で冷蔵保存していた…なんていう方も多いと思いますが、生の食感が楽しめる状態を最も長く楽しめる保存方法は、『50℃のお湯に浸ける方法』ですね。
50℃のお湯に浸ける処理をした後に冷蔵保存すると、皮が黒くなることもないですから、見た目にもおいしそうなバナナが楽しめます。
また、目先を変えて飽きずに食べきるためにも、お菓子にアレンジして冷凍するというのも良いですね。
繊維質、ビタミン、ミネラル、ポリフェノールと栄養が豊富で、美容や健康に良いバナナ。
常備しておきたい果物ですし、まとめ買いしたときには、利用の仕方にあった保存方法で、無駄なく食べきりたいですね。